どうした'?
「物質」とは、空間を占め(体積を持ち)、質量を持つすべてのものです。物質は、何らかの形で宇宙のあらゆるものを構成します。つまり、物質は宇宙のあらゆるものです。物質は、私たちの惑星と宇宙全体を構成します。
地球上では、すべての物質は固体、液体、気体の 3 つの異なる状態のいずれかで存在します。
人間は物質の3つの主要な状態すべてから構成されていることをご存知ですか?
物質が室温で存在する状態を標準状態といいます。たとえば、室温では水は液体として存在します。一部の物質は室温で気体として存在し (酸素と二酸化炭素)、他の物質は水のように液体として存在します。ほとんどの金属は室温で固体として存在します。水銀は標準状態では金属と液体の両方であるという興味深い特性を持っています。
これらの各状態は小さな粒子で構成されています。物質の状態は、それらが構成されている粒子の数によって決まります。
固体
通常、それ自体の形を保持でき、圧縮しにくいものは固体と呼ばれます。たとえば、固体の水は氷です。固体では、分子が密集しており、密度が高くなります。
液体
水のような液体は流れたり流れたりできますが、伸ばしたり圧縮したりすることはできません。液体では、分子は特に密集していますが、固体ほど密集していません。分子は動き回ったり、互いにすれ違ったりすることができます。液体には独自の形がなく、入れられている容器の形をとります。液体の例としては、水、牛乳、ジュース、ガソリン、レモネードなどがあります。
ガス
気体は流動し、膨張し、圧縮することができます。気体になった水は蒸気です。密閉されていない容器に入れば、蒸気は逃げてしまいます。気体の場合、分子は固体や液体よりもはるかに広がっており、互いにランダムに衝突します。気体はどんな容器にも入りますが、容器が密閉されていない場合は、蒸気は逃げてしまいます。気体は液体や固体よりもはるかに簡単に圧縮できます。
物質の状態の変化
物質は固体、液体、気体の状態で存在することができ、物質の状態は主に温度によって決まります。各物質には、状態が変化する固有の閾値温度があります。閾値温度を超えると、物質の相が変化し、物質の状態も変化します。一定圧力の条件下では、温度が物質の相を決定する主な要因となります。
物質は温度に応じて状態が変化します。融解、凍結、沸騰、蒸発、凝縮、昇華、沈殿は物質の状態が変化する方法です。
低温では、分子の運動は低下し、物質の内部エネルギーは低下します。分子は互いに低エネルギー状態に落ち着き、ほとんど動きません。これは固体の特徴です。温度が上昇すると、固体の構成部分に熱エネルギーが加わり、分子の運動がさらに起こります。分子は互いに押し合い、物質全体の体積が増加します。この時点で、物質は液体状態になります。温度上昇により分子が大量の熱エネルギーを吸収し、分子が自由に高速で互いの周りを動き回れるようになると、気体状態になります。
圧力が一定であれば、物質の状態はそれがさらされている温度に完全に依存します。このため、冷凍庫から氷を取り出すと溶け、鍋に長時間高温で放置すると水が沸騰します。温度は、周囲に存在する熱エネルギーの量を測るだけのものです。物質を異なる温度の環境に置くと、物質と周囲の間で熱が交換され、両者の温度が平衡に達します。そのため、氷が熱にさらされると、その水分子が周囲の大気から熱エネルギーを吸収し、より活発に動き始め、氷が溶けて液体の水になります。
融解は固体を液体に変えるプロセスです。固体が加熱されると、粒子にエネルギーが与えられ、より速く振動し始めます。特定の温度に達すると、粒子の振動が大きくなり、規則正しい構造が崩れます。この時点で、固体は液体に溶けます。固体から液体へのこの変化が起こる温度を融点と呼びます。各固体には、通常の気圧で融点が設定されています。山の上など気圧が低い場所では、融点は下がります。
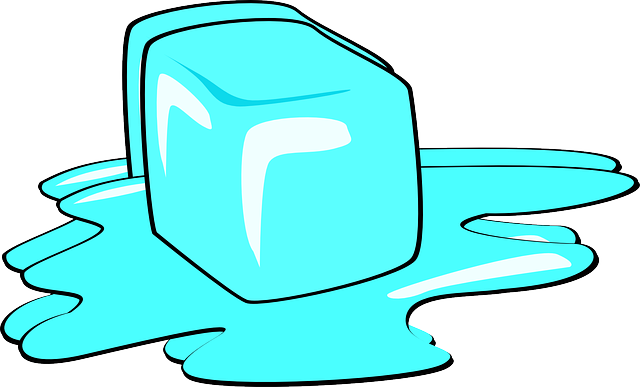
蒸発とは、液体を気体に変えるプロセスです。口の広い容器に水を入れておくと、しばらくすると水の一部が消えていくことに気づくでしょう。液体の水が気体(水蒸気)に変わるのが蒸発です。これは、液体が沸点よりはるかに低い温度で気体に変わるときに起こります。液体の中には、他の粒子から離れて気体になるだけのエネルギーを持つ粒子が常に存在します。
凝縮とは、気体を液体に変えるプロセスです。たとえば、寒い夜の翌朝、空気中の水蒸気は冷えて、葉や窓の上で小さな液体の水滴(露)に変わります。冷たい物体は、熱い物体からエネルギーを吸収することがよくあります。
凍結は液体を固体に変えるプロセスです。これは溶解の反対です。たとえば、溶岩は液体の岩石で、火山から 1,500 ℃ (2,732 ℉ ) もの高温で噴出します。しかし、赤熱した溶岩は地表に触れると冷えて、再び固体の岩石に戻ります。
沸騰– 液体が加熱されると、粒子にエネルギーが与えられます。粒子はより速く、より遠くまで動き始めます。ある温度に達すると、粒子は互いに離れ、液体は気体に変わります。これが沸点です。物質の沸点は常に同じで、変化しません。たとえば、水は沸点の 100ºC (212ºF) に達すると沸騰します。これは水が蒸気に変わる温度です。蒸気は目に見えない気体です。蓋に達すると冷却されて液体に戻ります。
昇華とは、固体が液体にならずに気体に変わることです。昇華の最も簡単な例はドライアイスかもしれません。ドライアイスは固体の二酸化炭素 (CO2) です。驚くべきことに、ドライアイスを部屋に置いておくと、液体にならずに気体に変わります。液体二酸化炭素について聞いたことがありますか? 液体二酸化炭素は作れますが、通常の状況では作れません。石炭は、通常の大気圧では溶けない化合物のもう 1 つの例です。非常に高い温度で昇華します。
沈着とは、気体が固体に変わることです。気体が液体状態を経ずに固体になるときに起こります。極地に近いところでは、冬の朝に霜が降りるのを見ることができます。植物の上の小さな霜の結晶は、空気中の水蒸気が植物の葉の上で固体になると形成されます。
化学変化と物理変化
化学的変化と物理的変化の違いを理解することが重要です。物理的変化は通常、物質の物理的状態に関するもので、化学変化は化学反応中に分子結合が破壊されたり生成されたりするときに起こります。化学変化は分子レベルで起こります。
分子に変化なし
輪ゴムを伸ばす、風船に空気を入れる、缶を潰す、これらはすべて物理的変化の例です。これらは物体の形状の変化のみです。分子レベルのエネルギーは変化していないため、物質の状態は変化しません。物理的変化では分子に変化は発生せず、分子は新しい化学結合が生成されたことも切断されることもなく、同じままです。
同様に、氷を溶かしたり、水を沸騰させたり、液体の水を凍らせたりすることも、すべてエネルギーを加えることによる物理的変化です。物質の相または状態の変化、つまり固体から液体、液体から気体、液体から固体の変化はすべて物理的変化です。温度や圧力の変化などの物理的作用は物理的変化を引き起こす可能性があります。たとえば、氷を溶かしたり、液体の水を凍らせたりしても化学変化は起こらず、水分子は依然として水分子のままです。
分子を変える
化学変化は、はるかに小さな規模で起こります。色の変化など、いくつかの実験では明らかな化学変化が見られますが、ほとんどの化学変化は目に見えません。過酸化水素 (H2O2) が水に変わる化学変化は、どちらの液体も透明なので見ることができません。しかし、その裏では、何十億もの化学結合が作られ、破壊されています。過酸化水素が水に変わると、酸素 (O2) ガスの泡が見えることがあります。これらの泡は化学変化の証拠です。
角砂糖を溶かしても、その物質は依然として砂糖であるため、物理的変化です。角砂糖を燃やすと、化学変化になります。火は砂糖と酸素の間の化学反応を活性化します。空気中の酸素が砂糖と反応し、化学結合が切断されます。
鉄が空気中の酸素ガスにさらされると、鉄は錆びます。このプロセスは長期間にわたって観察できます。鉄が酸化されるにつれて分子の構造が変化し、最終的に酸化鉄になります。廃墟の建物にある錆びたパイプは、酸化プロセスの実際の例です。
変化は可逆的なものもあれば不可逆的なものもある
可逆的な変化とは、元に戻すことができる変化のことです。たとえば、氷が溶けると水になりますが、再び凍らせて氷にし、元の状態に戻すことができます。可逆的な変化の例としては、溶解と加熱が挙げられます。
不可逆的な変化とは、元に戻すことができない変化のことです。たとえば、ケーキの混合物を焼くとケーキになり、混合物に戻すことはできません。化学反応が起こったため、変化は不可逆です。液体を燃焼させたり、重曹と混ぜたりすることは、不可逆的な変化の例です。
特定の用語と関連するフェーズの変更の簡単なスナップショット:
融合/溶解 – 固体から液体へ
凍結 – 液体から固体へ
蒸発/沸騰 – 液体から気体へ
凝縮 – 気体から液体へ
昇華 – 固体から気体へ
沈着 – ガスから固体へ